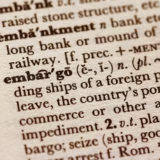こんにちは!スミスです。
2024年3月、日本銀行がマイナス金利を解除してから、住宅ローン金利を取り巻く環境は大きく変化しています。2025年1月には政策金利が0.5%程度に引き上げられ、長らく続いてきた超低金利時代は終わりを告げました。変動金利で住宅ローンを組んでいる方、これから借入を検討している方にとって、金利上昇は見過ごせない重要な問題となっています。本記事では、最新の住宅ローン金利動向を詳しく解説するとともに、変動金利ユーザーが今すぐ実践できるリスク対策を具体的にご紹介します。
住宅ローン金利の最新動向:2025年の状況
変動金利は横ばいだが上昇圧力が高まっている
2025年10月現在の住宅ローン金利は、変動金利については多くの銀行で据え置きが続いていますが、一部の銀行では金利が上昇する動きも見られました。具体的には、みずほ銀行では新規・借り換えともに前月比で0.25%の上昇、三菱UFJ銀行では借り換えのみ0.15%の上昇が確認されています(【2025年最新】住宅ローンの金利は今後どうなる?今後の金利上昇リスクを踏まえた住宅ローンの選び方 | 三菱UFJ銀行)。
2025年11月の変動金利(新規・借り換え)では、SBI新生銀行が年0.590%でトップとなり、調査した主要14銀行の住宅ローン金利について、2行が引き上げ、12行が金利を据え置きました。表面的には安定しているように見えますが、水面下では上昇圧力が確実に高まっている状況です(2025年以降の住宅ローン金利はどうなる?日銀の政策や今後の見通し解説 | 住宅ローン | SBI新生銀行,住宅ローンの金利推移(変動・固定)は? 最新の動向や金利タイプの選び方も解説【2025年】|ダイヤモンド不動産研究所)。
固定金利は明確な上昇トレンドに
変動金利が比較的安定している一方で、固定金利は異なる動きを見せています。2025年10月は、多くの金融機関で固定金利が先月より引き上げとなりました。主要銀行の10年固定は1.7~2.2%台で、前月比0.04~0.15%の上昇となっています。
長期金利(10年物国債の金利)は市場の金利見通しを反映するため、固定金利の上昇は投資家が将来の金利上昇を予想していることを示しています。これから住宅ローンを組む方にとって、金利タイプの選択はこれまで以上に重要な決断となっています。
金融機関間の金利競争は継続中
変動金利は、基準金利そのものは長らく大きく変わっていなかったものの、金融機関が契約者を獲得するために引き下げ幅を拡大し、適用金利を下げてきた歴史があります。2025年に入ってからも一部の金融機関では基準金利を引き上げる一方で、引き下げ幅を広げる動きが見られました。
このような金融機関間の競争環境により、借り換えでも新規借り入れと同様の優遇を受けられるケースが増えています。金利上昇局面だからこそ、複数の金融機関を比較検討する価値があります。
日銀の金融政策が住宅ローンに与える影響
マイナス金利解除と追加利上げの経緯
2024年3月19日に日銀はマイナス金利解除を決定し、2024年7月31日には政策金利の誘導水準を0.25%程度に引き上げ、2025年1月24日には政策金利の誘導水準を0.5%程度に引き上げを決定しました。これは17年ぶりの利上げであり、日本の金融政策が大きな転換点を迎えたことを意味します。
変動金利は短期プライムレート(優良企業への1年未満の短期貸し出しにおける最優遇金利)を指標にしており、この短期プライムレートは日銀の政策金利の影響を受けます。つまり、日銀の利上げは遅かれ早かれ変動金利に影響を及ぼすことになります。
今後の利上げの見通し
2025年10月29〜30日に開いた金融政策決定会合では、政策委員から「利上げをおこなうべきタイミングが近づいている」との意見があがり、「金利の正常化をもう一歩進めるうえで、条件が整いつつある」との声もありました。
金融政策決定会合の運営 : 日本銀行 Bank of Japan
2025年10月29日から30日にかけて行われた金融政策決定会合では、依然として政策金利の据え置きが発表されたものの、次回の金融政策決定会合(12月18日から19日開催予定)では0.25%金利の引き上げが行われるか、もしくは利上げが年明けに行われるか意見が分かれています。
賃上げは過去2年続いており、以前のデフレ時代とは異なり定着する可能性が高くなってきています。また、賃上げと同様、インフレも定着しつつあります。日銀は賃金とインフレの動向を注視しながら、段階的な利上げを進める方針とみられています。
短期プライムレートの実際の動き
2024年9月2日に短期プライムレートは1.625%に、2025年3月3日には1.875%に引き上げられました。これにより、一部の金融機関では変動金利の基準金利を引き上げる動きが出ています。ただし、各金融機関は優遇幅の調整により、実際の適用金利への影響を抑えようとしています。
変動金利ユーザーが知っておくべき5つのリスク対策
対策1:5年ルールと125%ルールを正しく理解する
変動金利で元利均等返済方式を選択している場合、多くの金融機関では「5年ルール」と「125%ルール」が適用されます。
- 5年ルール:金利が変更になっても、返済額は5年ごとの見直しまで変わりません(ただし元金と利息の内訳は変わります)
- 125%ルール:返済額の見直し時に、新返済額は前回までの返済額の125%が上限となります
一見すると安心できるルールに思えますが、注意が必要です。5年ルールにより、毎月の返済額は5年間変わりませんが、金利が上昇すると返済額に占める利息の割合が高くなるため、元本が減りづらい可能性があります。金利上昇分の利息は「未払利息」として蓄積され、後日支払う必要があるため、返済総額は確実に増加します。
※元金均等返済方式を選択している場合、5年ルールや125%ルールは適用されず、金利上昇がダイレクトに返済額に反映されます。自分の返済方式を必ず確認しましょう。
対策2:繰り上げ返済の戦略的活用
変動金利で今後利率の上昇が見込まれるタイミングには、金利上昇前に繰り上げ返済したほうがよいでしょう。元金が多いと、金利上昇に伴って支払利息も増えてしまいます。
繰り上げ返済には「期間短縮型」と「返済額軽減型」の2種類があります。
- 期間短縮型:返済期間を短縮する方法。利息軽減効果が高い
- 返済額軽減型:毎月の返済額を減らす方法。家計の負担を軽減できる
変動金利の住宅ローンは返済初期の段階でできるだけ早く「期間短縮型」の繰り上げ返済をするのが最も効果的です。返済初期は元金が多く残っているため、早めに繰り上げ返済することで将来の金利上昇リスクの影響を最小限に抑えられます。
繰り上げ返済の注意点
- 手元資金が減少するため、緊急時の備えは別に確保すること
- 金融機関によっては手数料がかかる場合があるため事前に確認すること
- 金利が1%以下かつ住宅ローン減税を利用している場合は、住宅ローン減税による控除額が利息額よりも大きくなるため、住宅ローン減税のほうが得になるか確認すること
- 変動金利の場合、金利上昇時に繰り上げ返済すると返済額が再計算され、逆に返済額が増える可能性があるため、タイミングに注意すること
対策3:金利上昇に備えた貯蓄の準備
変動金利住宅ローンを組んでいる場合、金利が上がれば毎月の返済額も増えるため、金利上昇に備えて一定額を毎月貯蓄しておくことがおすすめです。金利上昇により返済額が増えた際、貯蓄からすぐに支払えるようにすれば、家計への負担を軽減できます。
具体的には、現在の返済額と金利が1%上昇した場合の返済額の差額を毎月積み立てておくことで、実際に金利が上昇した際のクッションになります。また、この貯蓄は失業や病気などの緊急時の生活費としても役立ちます。
対策4:借り換えの検討
金利が上がるときは、今借りている金利も、借り換え先の金利もほぼ同時に上がることになります。ということは、利上げが行われた後も金利差は変わらないので、より低い金利に借り換えられるなら、ぜひしたほうがいいです。
借り換えを検討する際のポイント
- 金利差が大きい:一般的に1%以上の金利差があれば借り換えメリットが出やすい
- 残元本が多い:残高が1,000万円以上あると効果が大きい
- 残期間が長い:返済期間が10年以上残っていると有利
ただし、借り換えには事務手数料(一般的に借入額の2.2%程度)や登記費用などの諸費用がかかります。これらの費用を差し引いても得になるかをシミュレーションすることが重要です。
※変動金利から固定金利への借り換えは、金銭的なメリットよりも「金利上昇リスクへの不安を解消する」という精神的メリットが大きい選択肢です。どうしても金利変動が不安な方は検討する価値があります。
対策5:固定金利とのミックスプランの活用
全額を変動金利にせず、固定金利と組み合わせたミックスプランを選ぶことで金利上昇のリスクを抑えられます。ミックスプランとは、同一の金融機関から変動金利と固定金利をセットで借りる仕組みです。
ミックスプランのメリット
- 全額固定金利よりも低金利で借り入れができる可能性がある
- 金利の状況に合わせて、変動金利か固定金利の片方を繰り上げ返済することも可能
- リスク分散により、金利上昇時の影響を緩和できる
例えば、借入総額3,000万円の場合、2,000万円を変動金利、1,000万円を10年固定金利で借りるといった組み合わせが考えられます。これにより、変動金利のメリットを享受しながら、一定額は金利上昇リスクから守ることができます。
今後の住宅ローン金利はどうなる?専門家の見解
変動金利は緩やかに上昇する可能性が高い
2024年~2025年にかけて住宅ローン金利は上昇傾向です。2025年5月以降の金利については、今後も上昇する可能性が残っています。ただし、変動金利が急激に上がることは考えられにくく、1%前後の低金利時代が、しばらくの間、継続すると想定できますという見方もあります。
私の個人的な見解としては、日銀は海外経済の不確実性や国内経済への配慮から、急激な利上げではなく段階的な正常化を目指すと考えられます。そのため、変動金利は年0.1~0.2%程度ずつ緩やかに上昇していく可能性が高いでしょう。
固定金利は引き続き上昇トレンド
日銀は長期国債の買い入れ額を、2026年1~3月に向けて毎月4,000億円ずつ減額する計画を発表しており、長期金利は今後緩やかに上昇していくものと考えられます。指標となる長期金利が上がるにつれて、固定金利も上がる可能性が高いです。
これから住宅ローンを組む方で、金利変動リスクを避けたい場合は、固定金利がさらに上昇する前に早めに決断することも選択肢の一つです。
10年後、20年後の金利予測は困難
住宅ローン金利は、不動産市場だけではなく、物価や世界経済など、さまざまな要因を考慮して政策に反映されます。そのため、10年後・20年後を考えた場合、固定金利と変動金利のどちらを選んだほうが、お得なのかは、誰にもわかりません。
重要なのは、「どちらが得か」を予測することではなく、金利が上がった場合に備えて、無理のない住宅ローンの返済計画やリスク対策をおこなうことです。自分のライフプランや家計状況に合った金利タイプを選び、定期的に見直しを行うことが大切です。
金利タイプを選ぶ際の判断基準
変動金利が向いている人
- 収入が安定しており、金利上昇時にも余裕を持って対応できる
- 繰り上げ返済を積極的に行う予定がある
- 住宅ローンや金利動向に関心があり、定期的にチェックできる
- 比較的短期間(10~15年以内)で完済する予定がある
固定金利が向いている人
- 将来の収入が不確定で、返済計画を確実に立てたい
- 教育費など、今後大きな出費が予想される
- 金利変動を気にするストレスを避けたい
- 金利の見直しや借り換えの検討が面倒に感じる
参考記事リンク
- 三菱UFJ銀行「住宅ローンの金利は今後どうなる?」
- SBI新生銀行「2025年以降の住宅ローン金利はどうなる?」
- 日本銀行「金融政策決定会合の運営」
- ダイヤモンド不動産研究所「住宅ローンの金利推移」
- モゲチェック「住宅ローン金利2025年11月の最新動向」
※本記事の情報は2025年11月10日時点のものです。最新情報については公式サイト等でご確認ください。


![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1e4d4a6f.137bd27e.1e4d4a71.aabba349/?me_id=1213310&item_id=21418990&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0742%2F9784433720742_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1e4d4a6f.137bd27e.1e4d4a71.aabba349/?me_id=1213310&item_id=19859273&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F7532%2F9784534057532.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1e4d4a6f.137bd27e.1e4d4a71.aabba349/?me_id=1213310&item_id=15557450&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F9053%2F9784434159053.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)