こんにちは!スミスです。
「気づいたら貸金業務取扱主任者試験まで1週間しかない…」「もう間に合わないかも」と焦っていませんか?実は私も2022年の試験で、まさにそんな状況に陥りました。でも大丈夫です。正しい戦略で取り組めば、短期間でも合格は可能です。私は実際に勉強期間わずか1週間で28点(合格点28点)のギリギリ合格を果たしました。この記事では、その時の実体験と具体的な勉強法をお伝えします。同じような状況の方や、効率的な勉強法を知りたい方の参考になれば幸いです。
貸金業務取扱主任者試験の基本情報と私の状況
試験の概要と合格の難易度
貸金業務取扱主任者は、貸金業者(消費者金融、クレジットカード会社など)において必要とされる国家資格です。
日本貸金業協会は、貸金業務取扱主任者資格試験の実施に関する事務を行う指定試験機関として、平成21年6月に貸金業法に基づく内閣総理大臣の指定を受け、これまでに19回の試験を実施いたしました。
貸金業務取扱主任者 試験・講習・登録 | 日本貸金業協会
試験の基本情報は以下の通りです。
- 試験実施回数:年1回(11月中旬頃)
- 問題数:50問(4肢択一式)
- 試験時間:2時間
- 合格点:令和6年度(2024年度)合格者は2,998人
合格基準点50問中30問正解、合格率32.4%
(令和6年度(2024年度)貸金業務取扱主任者試験 合格発表!合格点30点 合格率32.4% – STUDYing)
近年の合格率は30%前後で推移しており、宅建士の合格率(15%前後)と比べると取り組みやすい国家資格と言えるでしょう。
私の試験当時の状況
2022年の試験で、私は以下のような状況でした。
- 勉強開始時期:試験の1週間前
- 法律知識:基礎レベル
- 勉強時間:毎日徹夜(※読者にはおすすめしません)
正直に言うと、この勉強方法は身体的にも精神的にも非常にきつく、健康を害する可能性があります。しかし、どうしても間に合わせなければならない事情がある方には、戦略的なアプローチとして参考になるかもしれません。
一般的な勉強時間との比較
通常、貸金業務取扱主任者試験に必要とされる勉強時間は、
- 初学者:180時間、業務経験者・民法などの学習経験者であれば60~120時間、勉強時間が必要
(【2025年最新】貸金業務取扱主任者の難易度は?合格率や勉強時間、偏差値も解説! | グッドスクール・資格取得情報比較) - 業務経験者:60~120時間
- 法律学習経験者:60~120時間
私の場合は約50時間程度(1週間×毎日7-8時間)でした。
1週間で合格するための戦略的勉強法
教材選択の重要性
短期間での合格を目指すには、教材選択が極めて重要です。私が採用した戦略は以下の通りです。
- テキスト:ほぼ読まず
- 問題集:メイン教材として使用
- 過去問:時間があれば確認程度
市販の問題集には、通常重要度や過去出題率が記載されています。私はその中でも「重要度A」や「過去出題率高」といった最重要問題のみに絞って学習しました。
捨て問戦略の実践
限られた時間で効率を最大化するため、「捨て問戦略」を徹底しました。
- 重要度の低い問題:完全に捨てる
- 出題頻度の少ない分野:基本事項のみ確認
- 複雑な計算問題:時間をかけずに基本パターンのみ
この戦略により、限られた時間を重要分野に集中投入することができました。結果的に28点というギリギリの点数でしたが、合格という目標は達成できました。
効率的な学習サイクル
1週間という短期間で知識を定着させるため、以下のサイクルを繰り返しました。
1日の学習パターン
- 午前(3-4時間):貸金業法の重要問題
- 午後(2-3時間):民法・その他法令
- 夜間(2-3時間):全分野の復習
同じ問題を短期間で何度も繰り返すことで、記憶の定着を図りました。※ただし、この学習量は身体への負担が大きいため、可能であればもう少し余裕を持ったスケジュールをおすすめします。
重要分野の攻略法と実践テクニック
貸金業法は絶対に落とせない分野
貸金業法は出題数が最も多く、合格の鍵を握る分野です。私はここだけは絶対に落とさないよう必死に取り組みました。
貸金業法で押さえるべきポイント
- 貸金業者の登録・更新
- 業務運営に関する規制
- 取立て規制
- 総量規制
- 契約書面・受取証書
特に数字が絡む規定(登録期間、利率制限、書面交付期限など)は暗記必須です。語呂合わせや覚えやすい方法を駆使して記憶に定着させました。
民法の効率的な学習法
民法は範囲が広いため、短期間では頻出論点に絞った学習が重要です。
- 債権・債務関係:保証、連帯保証
- 契約関係:売買、賃貸借
- 時効:消滅時効の期間
- 相続:法定相続分
民法は理屈で理解できる部分が多いので、丸暗記よりも「なぜそうなるのか」を考えながら学習しました。
その他の分野の対策
出題数の少ない分野については、以下の方針で対応しました。
出資法・利息制限法
- 利率の数字を正確に覚える
- 適用場面の違いを整理
割賦販売法・消費者契約法
- 基本的な概念のみ押さえる
- 細かい規定は捨て問として扱う
この戦略により、限られた時間で最大効率の学習を実現できました。
問題演習のコツ
短期間で実力をつけるため、以下の点を意識して問題演習を行いました。
- 間違えた問題はその場で解説を読む
- 正解した問題も解説を確認(理由が曖昧な場合)
- 似たような問題は関連付けて覚える
- 時間を計って解く習慣をつける
合格への心構えと今後の展望
ギリギリ合格の現実と教訓
私の2022年の結果は28点で合格点28点ちょうどというギリギリの合格でした。この経験から得た教訓をお伝えします。
- 合格は合格:点数に関係なく資格は取得できる
- 体調管理の重要性:無理な勉強は継続困難
- 戦略的学習の効果:時間がなくても工夫次第で合格可能
- 業務経験の価値:実務知識が大いに役立った
もし時間に余裕があるなら、もう少し計画的な学習をおすすめします。しかし、どうしても短期間で合格が必要な方には、私の方法も一つの参考になるでしょう。
学生や就活生へのメッセージ
貸金業務取扱主任者と宅地建物取引士ともに、合格には50問の設問中30問前後の正解数を求められます。しかし、合格率は貸金業務取扱主任者が30%前後なのに対して、宅地建物取引士は15%前後となっており、約半分の割合です。
貸金業務取扱主任者の難易度は?合格率や仕事内容についてもご紹介! | おすすめの資格や通信講座を比較|マイナビニュース資格
この資格は宅建よりも難易度が低い国家資格として位置づけられています。学生の方にとって、就職活動前に取得する資格としては非常におすすめです。
- 金融業界への就職に有利
- 法律知識の基礎が身につく
- 比較的短期間で取得可能
- 国家資格としての価値
継続的な学習の重要性
資格取得はゴールではなく、スタートです。実務で活かすためには、
- 法改正情報のチェック
- 実務での応用
- 関連資格の取得検討
- 継続的な知識アップデート
今後の試験対策へのアドバイス
これから受験を検討している方へのアドバイスです。
理想的な学習スケジュール
- 3ヶ月前:学習計画の策定と教材準備
- 2ヶ月前:基礎知識のインプット開始
- 1ヶ月前:問題演習中心の学習
- 直前期:弱点補強と最終確認
効率的な学習のポイント
- 出題頻度の高い分野を重点的に学習
- 問題集を中心とした実践的な学習
- 定期的な模擬試験で実力確認
- 体調管理を怠らない
私の1週間という極端な例は参考程度に留め、できる限り余裕を持った学習計画を立てることを強くおすすめします。しかし、どのような状況でも諦めずに戦略的にアプローチすれば、合格の可能性は十分にあります。
貸金業務取扱主任者は、金融業界でのキャリア形成に大いに役立つ資格です。ぜひチャレンジして、新たなステップを踏み出してください。
※本記事の情報は2025年9月23日時点のものです。最新情報については公式サイト等でご確認ください。
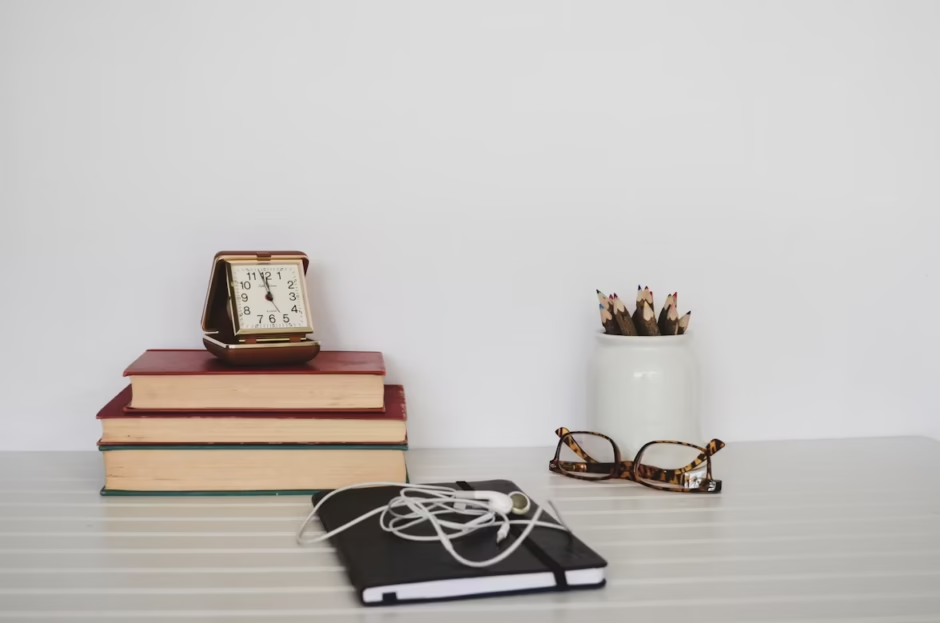

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1e4d4a6f.137bd27e.1e4d4a71.aabba349/?me_id=1213310&item_id=21559172&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F6760%2F9784300116760_1_34.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1e4d4a6f.137bd27e.1e4d4a71.aabba349/?me_id=1213310&item_id=21552133&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8386%2F9784297148386_1_26.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

