こんにちは!スミスです。
金融機関にお勤めの方なら、「内部管理責任者試験」という言葉を一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。管理職への登竜門とも言われるこの資格試験ですが、「難しそう」「どう勉強すればいいかわからない」と不安に感じている方も多いかもしれません。
実は私も最初は不安でいっぱいでしたが、正しい勉強法と心構えを持って臨めば、15時間程度の学習で合格することができました。この記事では、私自身の経験をもとに、効率的な試験対策の方法と、本番で焦らないための心構えをお伝えします。これから受験される皆さんが、自信を持って試験に臨めるよう、具体的なノウハウをご紹介していきます。
内部管理責任者試験とは何か
試験の基本情報と受験資格
内部管理責任者試験は、日本証券業協会が実施する資格試験です。
この資格は、支店や部署の営業活動等が適正に遂行されているかについて管理を行う非営業職の者に必要とされる資格で、金融機関の管理職を目指す方にとって重要な位置づけとなっています。
内部管理責任者 | 日本証券業協会
受験するためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 一種証券外務員資格を保有していること
- 日本証券業協会の協会員(証券会社や銀行など)に所属していること
- 所属企業を通じて受験申込を行うこと(個人での申込は不可)
試験は毎営業日に実施されており、全国の主要都市にあるテストセンターで受験できます。試験時間は90分で、50問が出題されます。合格基準は500点満点中350点以上(7割)です。
注意! 不合格となった場合、翌日から30日間は再受験できません。さらに3回連続で不合格になると、180日間(約半年間)の再受験禁止措置が取られます(内部管理責任者(内管)とは?取る必要がある? – STUDYing)。この点を考慮して、計画的に準備を進めることが大切です。
合格率と難易度の実態
内部管理責任者試験の合格率は、一般的に80~90%程度と言われています。この数字だけを見ると「簡単な試験なのでは?」と思われるかもしれませんが、油断は禁物です。
高い合格率の背景には、いくつかの理由があります。
- 受験者の多くが既に一種証券外務員資格を保有しており、試験範囲が重複している
- 外務員試験合格直後に、記憶が新しいうちに受験する人が多い
- 再受験制限があるため、しっかり準備してから受験する人が多い
- 会社から取得を求められるため、業務に関連する知識がある
つまり、合格率が高いのは試験が簡単だからではなく、受験者がきちんと準備しているからなのです。逆に言えば、準備不足で臨むと不合格になる可能性は十分にあります。実際に、勉強をほとんどせずに受験して落ちた同僚もいました。
試験範囲と出題形式
試験範囲は、日本証券業協会発行の「会員営業責任者・会員内部管理責任者必携」から主に出題されます(二種外務員資格試験受験概要)。具体的な出題分野は以下の通りです。
- 法令・規則:金融商品取引法、自主規制規則など
- コンプライアンス:法令遵守、倫理的な問題
- 内部管理体制:管理システム、規程の理解
- リスク管理:リスクマネジメントの知識
- 顧客管理:適合性の原則、顧客保護など
試験形式は、2択問題と4択問題の選択式です。計算問題よりも、倫理的・道徳的な判断や、法令遵守に関する知識を問う問題が中心となっています。一種証券外務員試験と重なる部分も多いため、外務員試験で学んだ知識が活きる場面も多くあります。
私が実践した15時間の勉強法
問題集を中心とした学習戦略
私が内部管理責任者試験に合格したときの勉強時間は、トータルで約15時間でした。この短期間で効率的に合格レベルに到達するために、私が最も重視したのは問題集の周回学習です。
具体的な学習手順は以下の通りです。
- 1周目:まずは全問題を解いてみる(正解・不正解は気にしない)
- 2周目:間違えた問題を中心に解き直し、解説をしっかり読む
- 3周目:再度間違えた問題のみを重点的に復習
この方法の利点は、実際の試験形式に慣れながら、効率的に知識を定着させられることです。テキストを最初から最後まで読む方法もありますが、内部管理責任者試験の場合、テキストを読んだだけでは実戦力が身につきにくいと感じました。問題を解くことで、どのような形式で知識が問われるのかを理解することが重要です。
ポイント! 問題集を選ぶ際は、必ず最新版を購入してください。金融関連の法令は頻繁に改正されるため、古い問題集では最新の法令に対応できません。
間違えた箇所をテキストで深掘りする
問題集を解いていると、必ず間違える問題や理解が曖昧な箇所が出てきます。そこで私が実践したのが、間違えた問題についてはテキストに戻って理解するまで勉強するという方法です。
この「問題集→テキスト」の往復学習が、知識の定着に非常に効果的でした。具体的には以下のステップで進めました。
- 問題集で間違えた問題の該当箇所をテキストで探す
- テキストの該当ページを読み込み、なぜその答えになるのかを理解する
- 関連する周辺知識もついでに確認する
- 理解できたら、もう一度同じ問題を解いてみる
単に問題集の解説を読むだけでは、表面的な理解にとどまってしまいます。テキストでしっかりと背景知識を学ぶことで、類似問題にも対応できる応用力が身につきます。
また、このプロセスを通じて、自分がどの分野が弱いのかも明確になります。私の場合は、コンプライアンスに関する倫理的判断の問題で迷うことが多かったため、その部分を重点的に学習しました。
最新版の教材を使うことの重要性
金融関連の法令は、年度によって改正されることが珍しくありません。特に金融商品取引法や自主規制規則などは、社会情勢や金融事件の発生に応じて頻繁に見直されます。そのため、テキストと問題集は必ず最新版を使用してください。
古い教材を使うリスクとしては、以下のようなことが考えられます。
- 法改正により、問題の前提条件や正解が変わっている可能性がある
- 新しく追加された法令や規則が出題されても対応できない
- 試験で出題される最新のトレンドやトピックを押さえられない
会社から支給される教材がある場合は、それが最新版かどうかを必ず確認しましょう。もし不安な場合は、書店やオンラインで最新の問題集を購入することをお勧めします。数千円の投資で合格の確実性が高まるなら、決して無駄な出費ではありません。
本番で焦らないための心構え
問題集にない問題が出ても大丈夫
ここからは、試験本番での心構えについてお話しします。実は私自身、本番の試験を受けたとき、問題集では見たことがないような問題が複数出題されました。最初は「えっ、こんな問題見たことない!」と焦りましたが、冷静に対応することで無事に合格できました。
問題集に載っていない問題が出る理由としては、以下のようなことが考えられます。
- 試験問題はプール制で、幅広い問題の中からランダムに出題される
- 問題集はあくまで「予想問題」であり、全ての問題を網羅しているわけではない
- 最新の法改正や時事問題に関する問題が追加される
大切なのは、見たことがない問題が出ても動揺しないことです。全ての受験者が同じ条件で受験しているわけですから、難しい問題は他の受験者にとっても難しいのです。焦って適当に答えを選ぶのではなく、落ち着いて問題文を読み、持っている知識を総動員して考えましょう。
7割正解を目指す現実的な目標設定
内部管理責任者試験の合格ラインは、50問中35問正解(7割)です。これは言い換えれば、15問は間違えても合格できるということです。この事実を理解しておくことが、試験本番での精神的な余裕につながります。
私が試験を受けたときに心がけていたのは、以下のような考え方です。
- 全問正解を目指す必要はない。7割取れば十分
- どうしてもわからない問題は、深追いせずに次に進む
- 時間配分を意識し、1問に時間をかけすぎない
- 確実に解ける問題を落とさないことを最優先にする
試験時間は90分、問題数は50問ですから、1問あたり約1分48秒使えます。難しい問題で悩む時間があるなら、確実に正解できる問題を見直す時間に充てる方が、合格への近道です。
また、試験はコンピューター形式なので、後で見直しができる機能もあります。わからない問題はマークして後回しにし、最後に時間が余ったら考え直すという戦略も有効です。
常識的な判断で正解率を上げる
内部管理責任者試験の問題には、倫理的・道徳的な判断を問うものが多く含まれています。こうした問題では、細かい法令知識よりも、「金融機関の職員として、どう行動すべきか」という常識的な判断が重要になります。
私が試験を受けた経験から言えるのは、迷ったときは常識的に考えることで正解する確率が高いということです。具体的には、以下のような基準で判断すると良いでしょう。
- 顧客の利益を最優先に考える選択肢を選ぶ
- 法令遵守を重視する選択肢を選ぶ
- 透明性や説明責任を果たす選択肢を選ぶ
- リスクを適切に管理する選択肢を選ぶ
重要! 逆張りは厳禁です。「この選択肢は当たり前すぎるから違うかも」と考えて、わざと常識外れの選択肢を選ぶのは避けましょう。試験は奇をてらった問題を出すためのものではなく、適切な判断力があるかを確認するためのものです。
また、選択肢の中に「絶対に」「必ず」「一切」といった極端な表現が含まれる場合、それは不正解である可能性が高いです。逆に、「適切に」「原則として」「状況に応じて」といった柔軟な表現が含まれる選択肢は、正解の可能性が高くなります。
試験を突破するための総まとめ
油断大敵!でも恐れる必要はない
ここまでお読みいただいた方には、内部管理責任者試験が「合格率が高いから簡単」というわけではないことがお分かりいただけたと思います。油断していると落ちる試験であることは間違いありません。
しかし同時に、正しい準備をすれば恐れる必要はない試験でもあります。私自身、15時間という短期間の学習で合格できたのは、以下の点を意識していたからです。
- 問題集を中心とした効率的な学習法を実践した
- 間違えた箇所はテキストで理解するまで勉強した
- 最新版の教材を使用し、法改正に対応した
- 本番では7割正解を目標に、焦らず冷静に対応した
- 常識的な判断を大切にし、奇をてらった選択は避けた
これらのポイントを押さえて学習すれば、多くの方が短期間で合格レベルに到達できるはずです。
受験制限を考慮した計画的な準備
前述の通り、内部管理責任者試験には受験制限があります。不合格後30日間は再受験できず、3回連続不合格の場合は180日間の受験禁止となります。この制限は、人事評価や昇進にも影響する可能性があるため、できるだけ1回で合格することを目指しましょう。
そのためには、以下のような計画的な準備が重要です。
- 試験日の2~3週間前から学習を開始する
- 最低でも10~20時間の学習時間を確保する
- 問題集を最低3周は解く
- 会社の業務が忙しい時期を避けて受験日を設定する
- 体調管理にも気を配り、万全の状態で試験に臨む
特に、一種証券外務員試験に合格した直後であれば、知識が新鮮なうちに内部管理責任者試験も受験することをお勧めします。試験範囲が重複している部分が多いため、効率的に学習を進められます。
自信を持って試験に臨むために
最後に、これから受験される皆さんにお伝えしたいのは、自信を持って試験に臨んでほしいということです。
内部管理責任者試験は、決して乗り越えられない壁ではありません。多くの先輩方が合格してきた道です。この記事でご紹介した勉強法と心構えを参考にしていただければ、皆さんも必ず合格できるはずです。
試験当日は、以下のことを心に留めておいてください。
- 問題集にない問題が出ても動揺しない
- 7割正解で合格できることを忘れない
- わからない問題は深追いせず、次に進む
- 常識的な判断を大切にする
- 時間配分を意識し、見直しの時間を確保する
試験終了後は、その場で正答率が表示されますので、すぐに結果がわかります。70%以上であれば合格です。合格の瞬間の喜びを、ぜひ味わってください!
皆さんの合格を心よりお祈りしています。この記事が、少しでも試験対策のお役に立てれば幸いです。頑張ってください!
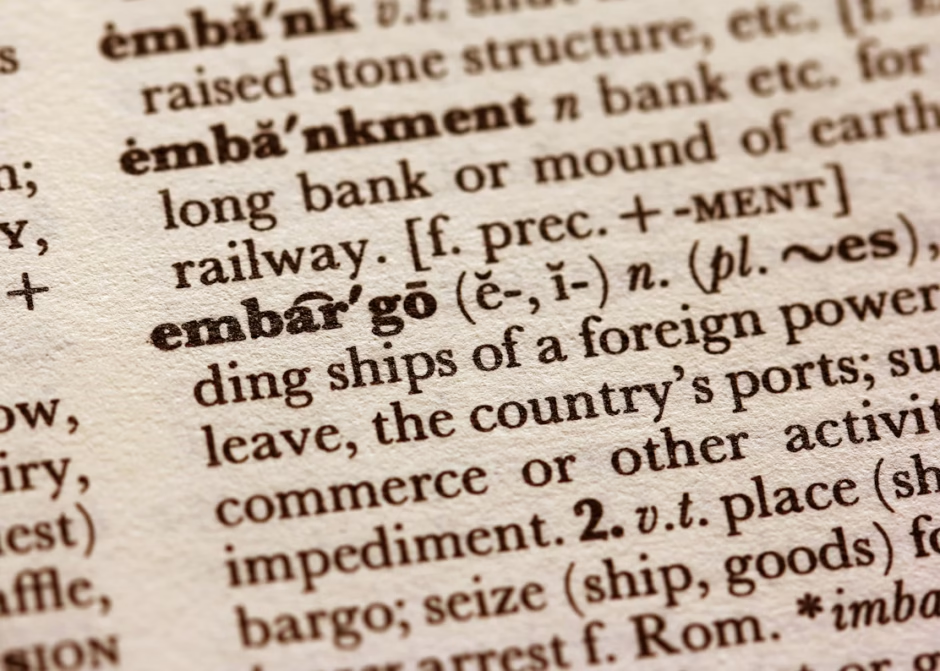

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1e4d4a6f.137bd27e.1e4d4a71.aabba349/?me_id=1213310&item_id=21433808&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0862%2F9784828310862_1_67.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4d774bfb.d912db5e.4d774bfc.00ef212a/?me_id=1285657&item_id=12994672&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbookfan%2Fcabinet%2F01139%2Fbk4828310878.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

